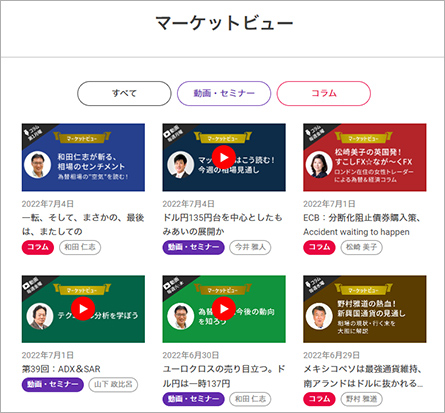あなたはいくら貯めている?20代、30代、40代、50代の平均貯金額を公開!


ファイナンシャルプランナー1級・AFP・日商簿記2級・年金アドバイザー3級
木内 菜穂子 氏
金融機関、税理士事務所、救急医療系財団法人を経て、結婚を機に退職。現在は、金融・保険ライターとして4年半ほど執筆活動中。
自分と同じ年代の人が、どのくらいの貯金があるのか、その平均値や中央値が気になりませんか?自分の貯金額と比べてどうなのか、知りたい人もいるでしょう。
そこで今回は、20代から50代までの世代ごとの貯金額の平均値や中央値を紹介したうえで、実際のアンケート結果を元に、リアルな貯金事情も紹介します。
また、より効果的に自分の資産を増やしていく方法も、併せて確認していきましょう。
貯金額を見る前に。平均値と中央値をおさらい
冒頭で貯金の「平均値や中央値」という言葉を使いましたが、まず「平均値」と「中央値」の違いを確認しておきましょう。
平均値とは
データの数値をすべて合計して、データの個数で割った値のことです。
データ全体のイメージをつかみやすいですが、極端な値の影響を受けやすいというデメリットがあり、現実とかけ離れた結果が出てしまうこともあります。
たとえば、3つの商品が40万円、50万円、60万円だった場合の平均値は50万円ですが、この中に120万円の商品が加わると、平均値は67万5,000円と、他の商品の価格よりずいぶん高くなります。
平均値はデータの中心の値を示すとは限らないということになり、そこで「中央値」という考え方が必要になります。
中央値とは
読んで字のごとくデータの中央に位置している数値のことで、データを大きい方、または小さいほうから順番に並べたときに真ん中に位置している数値のことです。
例えば、データ数が5個の場合は、左から3番目イコール右から3番目、つまり真ん中の値が中央値になります。
データ数が6個の場合は、真ん中にくるデータがふたつになってしまうため、このふたつの平均値を中央値とします。
他のデータから大きく外れた値が及ぼす影響をなくして、大体中心の数値がわかるメリットがある反面、データ全体の分布状況のイメージを持ちづらいというデメリットがあります。
世代別の平均貯金額を知るにはどちらのデータも参考になりますので、さっそく20代の平均貯金から確認していきましょう。
なお、これから紹介する各年代別の平均貯金については、以下のデータを参考にしています。
【参考】
また、独自に20代から50代の人に貯金についてのアンケートを行いましたので、その結果も紹介します。
【アンケート概要】
- 調査時期:2021年7月1日~7月7日
- 回答数:286件
- 調査手法:インターネット調査
20代の貯金額の平均・中央値は?
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、20代の貯金額の平均値と中央値は、「単身者」と「二人以上世帯者」でそれぞれ以下のような結果となっています。
【20代の貯金額】(単位:万円)
| 項目 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 平均値 | 113 | 292 |
| 中央値 | 8 | 135 |
単身者・二人以上世帯者ともに平均値と中央値が大きく離れていることがわかります。
貯金額の細かい分布を見ると、以下のように分かれています(単位:%)。
| 貯金額 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 28.3 | 20.0 |
| 100~200万円未満 | 8.8 | 16.0 |
| 200~300万円未満 | 4.8 | 12.0 |
| 300~400万円未満 | 3.6 | 0.0 |
| 400~500万円未満 | 2.5 | 12.0 |
| 500~700万円未満 | 2.9 | 12.0 |
| 700~1,000万円未満 | 1.7 | 4.0 |
| 1,000万円以上 | 4.2 | 4.0 |
単身者では100万円未満の人が28%、二人以上世帯者では100万円未満が20%で、200万円未満が16%を占めています。
20代のリアルな貯金事情
アンケ―トでは、20代の男女53人から回答を得ることができました。
現在の貯金額についての質問については、0円から800万円までさまざまで、「今度どのくらい貯金をしたいか」という質問では、1,000万円や2,000万円といった金額にとどまらず、5,000万円や1億円と回答した人もいました。
また、貯金や節約のために、以下のようなことを実践しているようです。
- ポイ活をする
- 先取り貯金をする
- 積み立てNISAで貯蓄する
- 還元キャンペーンがあるキャッシュレス決済を利用する
- 昼食は弁当・水筒を持参する
- 自炊をして外食を控える
それぞれ工夫を凝らして貯金や節約をしていることがわかります。
30代の貯金額の平均・中央値は?

続いて、「家計の金融行動に関する世論調査」の30代の平均貯金額を見てみましょう。
【30代の貯金額】(単位:万円)
| 項目 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 平均値 | 327 | 591 |
| 中央値 | 70 | 400 |
金額の詳しい分布は下表を参考にしてください。(単位:%)
| 貯金額 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 19.9 | 9.1 |
| 100~200万円未満 | 9.4 | 10.0 |
| 200~300万円未満 | 5.9 | 11.7 |
| 300~400万円未満 | 4.1 | 10.8 |
| 400~500万円未満 | 4.6 | 10.0 |
| 500~700万円未満 | 6.4 | 11.3 |
| 700~1,000万円未満 | 5.7 | 8.7 |
| 1,000万円以上 | 13.0 | 20.4 |
単身者では100万円未満の人が20%いる一方で、1,000万円以上の人が13%います。
二人以上世帯者では、100万円単位でほぼ均等に分布しており、1,000万円以上貯金のある世帯が20%を超えています。
30代のリアルな貯金事情
アンケートでは、30代の男女114人から回答を得ることができました。
現在の貯金額の幅は2万円から2,800万円と20代よりもさらに広くなっており、10万円未満の人が数名いる一方で、2,000万円超の人が15人いました。
また、今後どのくらい貯金をしたいかという質問には、1,000万円から2,000万円と回答した人が多く、1億円を目指している人もいました。
現在、貯金や節約のために取り組んでいることとして、以下のことがあるようです。
- 貯蓄口座を作ってボーナスを貯めている
- 格安スマホに変えた
- 副業やポイ活をしている
- 家計簿をつけている
- 固定費の削減をする
- 株やFXをしている
無駄遣いをしないよう気を付ける一方で、副業や株、FXなどで資産を積極的に増やす取り組みをしている人もいます。
40代の貯金額の平均・中央値は?
「家計の金融行動に関する世論調査」で40代の平均貯金を見てみましょう。
【40代の貯金額】(単位:万円)
| 項目 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 平均値 | 666 | 1,012 |
| 中央値 | 40 | 520 |
詳しい貯金額の分布はこちらです。(単位:%)
| 貯金額 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 15.2 | 8.7 |
| 100~200万円未満 | 5.9 | 6.5 |
| 200~300万円未満 | 4.3 | 7.3 |
| 300~400万円未満 | 3.6 | 5.1 |
| 400~500万円未満 | 1.8 | 5.4 |
| 500~700万円未満 | 6.4 | 8.7 |
| 700~1,000万円未満 | 4.3 | 9.0 |
| 1,000~1,500万円未満 | 5.5 | 12.7 |
| 1,500~2,000万円未満 | 3.6 | 7.3 |
| 2,000万円以上 | 8.2 | 12.7 |
単身者では100万円未満の人が15%と最も多い一方、2,000万円以上貯金のある人が8%います。貯金をしている人と、していない人の差がはっきりと出てきています。
二人以上世帯者で最も多いのが「1,000万円~1,500万円未満」で12.7%、2,000万円以上の世帯も12.7%となっており、単身者と比較して貯蓄への意識が高いことがわかります。
40代のリアルな貯金事情
アンケートでは、40代の男女86人から回答を得ることができました。
現在の貯金額の幅は0円から2,500万円までと広く、1,000万円以上の貯金がある人は16人いました。
今後貯めたい金額は、1,000万円から3,000万円が多く、最も多い人で5,000万円でした。一方で、専業主婦などでは100万円以下に目標を設定している人も見られました。
主な節約術や貯金術として、以下のようなことに取り組んでいるようです。
- コンビニではなくスーパーで買い物をする
- 水道光熱費などを節約する
- つみたてNISAや株式投資をする
- フリマアプリで不用品を売る
- 個人型確定拠出型年金をしている
- 「500円玉貯金」や「つもり貯金」をする
40代でもさまざまな節約術を用いて貯金額を増やしているほか、つみたてNISAや株式投資などで積極的な運用をしている人もいます。また、個人型確定拠出型年金を始めるなど、老後資金の準備が気になるのも40代の特徴といえるでしょう。
50代の貯金額の平均・中央値は?
「家計の金融行動に関する世論調査」で、50代の平均貯金を見てみましょう。
【50代の貯金額】(単位:万円)
| 項目 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 平均値 | 924 | 1,684 |
| 中央値 | 30 | 800 |
詳しい貯金額の分布はこちらです。(単位:%)
| 貯金額 | 単身者 | 二人以上世帯者 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 10.4 | 6.4 |
| 100~200万円未満 | 4.8 | 5.3 |
| 200~300万円未満 | 3.3 | 5.3 |
| 300~400万円未満 | 3.5 | 2.8 |
| 400~500万円未満 | 2.8 | 3.4 |
| 500~700万円未満 | 5.3 | 8.3 |
| 700~1,000万円未満 | 5.6 | 9.2 |
| 1,000~1,500万円未満 | 5.3 | 11.7 |
| 1,500~2,000万円未満 | 3.0 | 5.7 |
| 2,000万円以上 | 11.9 | 24.6 |
単身者は100万円未満の人が10.4%いる一方、2,000万円以上貯金がある人は11.9%となっています。
二人以上世帯者では2,000万円以上の貯金がある世帯が24.6%と最も多く、次いで1,000万円から1,500万円未満が11.7%となっています。
50代のリアルな貯金事情
アンケ―トでは、50代の男女33名の回答を得ることができました。
現在の貯金額の幅が、10万円から2,000万円までと広いのはほかの世代と同様ですが、数百万円の貯金額がある人の割合が大きく、貯金への意識が高いといえます。
今後貯めたい金額は、1,000万円から2,000万円と回答した人が多く、1億円を目指している人もいました。
具体的な節約術や貯金術として、以下のようなことに取り組んでいるようです。
- 袋ごとに「食費」「通信費」「ガソリン代」など、分けて管理している
- ポイ活やクーポンなどを活用する
- 格安SIM携帯に乗り換えた
- 家の中の断捨離をして余計なものは買わないようにする
- 電気会社を安いところに乗り換えた
- 会社の財形貯金を活用している
- 株やその他の投資など
格安SIM携帯や安い電気会社に乗り換えて節約したり、会社の財形貯蓄や株などに投資して資産を増やしているようです。「断捨離」というワードが出るのも50代ならではといえるでしょう。
自身の資産をより増やしていくために
自分の資産を増やすためには、もちろん節約が大事です。前章で紹介したように、各世代で、さまざまな工夫をこらして節約に取り組んでいることがわかります。
しかし、より効率よく資産を増やすには、「投資」を行うこともひとつの方法です。
使う金額、特に固定費を下げる
毎月の固定費は「生活に欠かせないものだから節約できないのでは?」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、実は見直せる固定費は多くあります。固定費の見直しは即効性が高いというメリットもあるので、ぜひこの機会に見直しましょう。
■住居費
住居費には、賃貸物件に住んでいる場合の「家賃」と、持ち家に住んでいる場合の「住宅ローンの支払い」があります。
賃貸物件に住んでいる場合は、家賃が収入に対して適切かを判断しましょう。一般的に、住居費は収入の3分の1が目安とされていますので、月収が30万円の人の家賃は10万円までとするのが理想です。
もし月収に見合わない家賃を支払っているのであれば、家賃の安い物件に引っ越し、負担を軽減することを検討しましょう。
また、住宅ローンを支払っている場合は、繰り上げ返済することで住宅ローンの借入元金が減り、支払利息を少なくするので、余裕のあるときに積極的に繰り上げ返済をすると良いでしょう。
■光熱費
電気代やガス代などは、使わないときはこまめに消したり極力使わないようにしたりすることももちろん節約につながりますが、より効率よく節約するには電気会社やガス会社を見直すこともおすすめです。
電気代は、電力自由化に伴い「新電力」といわれる新規参入の電気会社がたくさんあり、ガス代などのほかのサービスと併用することでさらに割引となるところもあります。一度シミュレーションをしてみて、より安くできるところを選ぶと良いでしょう。
また、冷蔵庫やエアコンなどを省エネ家電に買い替えると、一時的な出費にはなりますが、電気代が節約できることが多いです。
■保険料
生命保険料や車の任意保険などは、万が一の場合に備えるものなので解約はできませんが、「保障(補償)の見直し」をすることで保険料を安くすることができます。
たとえば、複数の保険に加入している場合、保障が重複していることがありますので、保険料をムダに支払っている可能性があります。
同様に、車の任意保険でも、運転する人の年齢や免許証の色などに応じてさまざまな割引制度が用意されていますので、補償の見直しも兼ねて契約内容を確認しましょう。
投資についても考える
紹介してきたような節約をすると同時に、株式投資や不動産投資などの「投資」を行い、積極的な資産運用を始めてみるのも良いでしょう。
■株式投資
株式投資のメリットとして、購入した株券が値上がりしたタイミングで売却し「値上がり益」を狙える「キャピタルゲイン」や、企業の業績が良かったときに株主に配当金が還元される「インカムゲイン」、「株主優待」が受けられるといった3つのメリットがあります。
反対にデメリットとして、「価格変動リスク」や「流動性リスク」があることや、投資額が高額なケースが多いので、まとまった資金が必要という点があります。
■不動産投資
不動産投資は、値上がり益を狙うこともできますが、安定した家賃収入を得られるというメリットがあります。また、生命保険代わりに利用できたり、所得税や相続税の節税対策にも役立ったりします。
反対に、「空き室リスク」や「不動産価格下落リスク」、「資産流動化リスク(売りたくてもなかなか売れない)」といったデメリットがあり、さらに住宅ローンを組むことがほとんどのため、収益が悪化するとローンの返済ができなくなる可能性があります。
■株式・不動産投資以外の投資は?
株式投資や不動産投資について簡単に紹介しましたが、まとまった資金がないために株式投資ができない人や、不動産投資で住宅ローンを組みたくない人でも、手軽に投資ができるものに「FX」があります。
次章ではFXについて詳しく解説していきます。
FXという選択肢

FX(外国為替証拠金取引)とは、外国為替取引を「証拠金」を用いて行う取引のことで、取引を始めるにあたり、FX会社に「証拠金」を預け入れます。FXは、「差金決済」で利益を狙うため、現金の受渡しはなく売買の損益の受渡しだけで取引が行われます。
では、FXの主な特徴について見ていきましょう。
自動売買も活用できる
FX会社では、「自動売買」というサービスを行っており、あらかじめ登録をしておけばシステムが自動的に取引を行ってくれます。そのため、夜中や明け方でもムリして起きる必要がなく、寝ながらにして取引ができるのです。また、昼間の仕事中に取引をしたい場合も、本業に差しつかえることなく取り組むことができます。
24時間取引可能
日本の市場は9時から15時までとなっていますが、それ以外の時間でも他国の市場で取引が行われているため、平日であれば基本的に24時間FXの取引ができます。特に、ニューヨーク市場とロンドン市場が重複する時間帯(21時から午前3時頃まで)は取引が活発に行われるため、昼間は仕事で忙しい人でも仕事終わりにじっくりとFXに取り組むことができます。
レバレッジも活用できる
FXには「レバレッジ」という仕組みがあります。レバレッジとは、FX会社に預けた証拠金を担保にし、何倍もの金額を取引することができるというものです。この仕組みを活用すれば、少額でも大きな取引ができるため、株式投資のようにまとまった資金がなくても始められるのです。日本では最大25倍のレバレッジがかけられるので、たとえば証拠金に10万円を預けた場合は250万円までの取引が可能となります。
ただし、ハイリターンな取引にはハイリスクがつきものですので、リスクについて十分に理解したうえで取引をすることが大切です。